最近HSPってよく聞くけど、
もしかして私ってHSP?
HSPは生きづらいと耳にしたことがあるけれど、
本当なのかな
この記事では、そんな疑問を抱く方へ向けて、HSPの基礎をお伝えします。
自分の特性を知ることで、何を避けるべきか・何を大切にすべきかのヒントが得られますよ。
- HSPとは何?どういった特性がある?
- HSPの診断方法
- HSPが生きやすくなるにはどうするか
HSPとは
Highly Sensitive Personの頭文字を取ってHSPと呼びます。
直訳すると「とても敏感な人」
アメリカの心理学者である、エレイン・N・アーロンが1996年に提唱した概念で、感受性が強く、敏感な気質を持った人のことを表しています。
日本では「繊細さん」と呼ばれたりもしますね。感受性の強い上位約15~20%の人を指しています。
感受性は遺伝や環境などから、12歳ごろまでに形成されるのではないかと言われています(飯村周平,HSPの心理学,2022)。
HSPの4つの特性「DOES」
HSPの提唱者であるエレイン・N・アーロンが唱えた、HSPの代表的な4つの特性が「DOES」と呼ばれます。
Depth of processing : 処理の深さ
Overstimulation : 刺激に過敏
Emotional reactivity : 情緒的反応が強く、共感力が高い
Sensing the subtle : 些細なことも察知する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
D:処理の深さ
一つ目のDはDepth of processingのことで、「物事を深く考えて、慎重に判断する」ことを表しています。
HSPの人は、あらゆることを、過去の似たような経験と関連づけたり比較したりし、深いレベルで処理をする特性があります。
意識的にも無意識的にも、あらゆることを自分の経験と関連付けているのです。
深く考えることはよい一面もありますが、考えすぎてしまい行動にうつすまでに時間がかかるといったデメリットを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 1つのことを聞いて様々な予想を立てられる
- 考えすぎたとよく言われる
- 何かを始める際、じっくりと考える
- あれこれ考え過ぎて、決断に時間がかかる
 ゆるこ
ゆるこ私の場合、
・やってみたいことがあっても考えすぎて行動できない
・不測の事態に備えて、荷物が多い
・相手のちょっとした言動が気になり、考えすぎる
・色々なことが気になり、処理が遅い
などがよくあります。
O:刺激に敏感
2つ目のOは、Overstimulationであり、「刺激に過敏である」ことを指します。
HSPの人は、そうでない人と比べて刺激を受けやすい特性があります。
HSPではない人にとっては何ともないことでも、HSPさんには強い刺激となりストレスを感じてしまいます。
- 旅先で一日中観光するのは疲れる
- 飲み会やパーティが苦手
- 周囲の音が気になり集中できない
- 忙しい日が続くと不調になる
4つの特性の中でも、ネガティブな側面が強く感じられますね。
自分がどの程度の刺激に耐えられるのか、どの程度ストレスを感じるのかを知ったうえで対処していくことが大切です。



私の場合は、
・飲み会から帰るとぐったり
・休日に一日中出かけるのは疲れる
・人込みが苦手
などがよく実感する特性です。
E:情緒的反応が強く、共感力が高い
3つめのEはEmotional Reactivity。
喜怒哀楽に敏感に反応する特性を指します。
ポジティブ・ネガティブ両方に反応しますが、とくに、ポジティブな感情に対して強く影響を受ける傾向があります。
また、他人よりも親しい人、不幸せな表情よりも幸せな表情により強い反応を示します。
- 家族が喜んでいたら自分のことのように嬉しい
- ドラマや映画の影響を受けやすい
- 泣いている人を見ると自分も悲しくなってくる
- 誰かが怒られていると自分も辛い



私の場合、
・悲しいドラマを見ると1週間ほど引きずる
・家族の笑顔を見ると元気になる
・人に喜んでもらえると幸せ
などがよくあります。
ネガティブに引っ張られてしまうと辛いですが、ポジティブなことに共感できるのはHSPだからこそ得られるメリットかもしれませんね。
親しい人の幸せが自分の幸せになるって、とても素敵なことだと思います。
S:些細なことも察知する
最後のSは、Sensing the Subtle。
他人が見逃している些細なことにも気づくという特性です。
五感が優れているというよりは、感覚情報を慎重に処理しているという表現が適していると考えられます。
小さなことに気付くということはそれだけ気遣いができたり、ミスのない仕事に繋がったりするメリットもあります。
その反面、色々なことに気付き、気にしすぎてしまうといった負の側面を感じてしまう場合も。
- 人が気付かない些細なミスを発見する
- 困っている人を見つけやすい
- 明るい部屋では眠れない
- 時計の針の音が気になる



私の場合、
・人が何をしようとしているのかよく気が付く
・小さな音が気になって勉強に集中できない
・人の些細な表情の変化に気付く
などがよくあてはまります。
HSPかどうかチェックするには
DOESの特性には当てはまる気がするけれど、実際に私はHSPなのかな?と疑問に思う方もいらっしゃいますよね。
HSPかどうかを確認する手段として、いくつかのセルフチェックがあります。
※あくまでも心理テストなので、必ずしもこのチェックに当てはまることがHSPの条件というものではありません。
エレイン・N・アーロンのチェックリスト
代表的なチェックリストは、HSPの提唱者である、アーロン博士が作成したものです。
「自分をとりまく環境の微妙な変化によく気づくほうだ」
「一度にたくさんのことを頼まれるのがイヤだ」 など27項目で構成されています(Aron,1996)。
14以上の質問に「はい」であればおそらくHSPと言われています。
以下のサイトから日本語訳されたチェックリストが見られます。
Are You Highly Sensitive? (coocan.jp)
HSPを学べる本
HSPについてもっと知りたい、学びたい!と思った時におすすめの本を紹介します。
心理学の概念であるため、「HSPなら絶対に全てあてはまる!」というものではなく「HSPにはこういう傾向がある」というように、参考程度に読むことがよいでしょう。
HSPの心理学/飯村周平
日本の心理学者である飯村さんによって書かれた本で、科学的根拠に基づくHSPの知識が学べます。
大学生などでHSPをきちんと学びたい、という人にはまず読んでおいて損はない本だと思います。
敏感すぎる私の活かし方/エレイン・N・アーロン
HSPの提唱者である、アメリカの心理学者エレイン・N・アーロンの本です。
HSPが無意識に感じていることを掘り下げ、対処法を示してくれます。
敏感な世界に生きる 敏感な私たち/イルセ・サン
心理療法士イルセ・サンの著書。
ありのままの自分を好きになり、自分にとって過度な刺激が発生しないように環境を整える必要があると教えてくれる本です。
ポイントHSPは病気なのか?誤解しやすいポイント



HSPにあてはまりそうだけど、治すことはできるのかな?
HSPは環境からの影響の受けやすさという気質であり、病気ではありません。
治す・治せないといったものではないため、自分の気質を理解しうまく付き合っていくことが大切です。
病気との違いを知る
まず理解しておくべきなのは、HSPと精神疾患は別物ということです。
- HSPは心理学的な概念
- 精神疾患は精神医学的な病気
病気の兆候があるにもかかわらず、「これはHSPの特徴だから病気ではない!受診の必要はない!」と思ってしまうことは危険です。
精神疾患は早期治療により回復が早まることが期待できます。
過度に生きづらさを感じる・日常生活に支障をきたすほどの症状が出ているなどの場合、受診を検討することが大切です。
よくある精神疾患の例を挙げます。これ以外にも、違和感や不安を抱いたら一度専門家に見てもらうことがよいでしょう。
うつ
2週間に渡り、以下のような状態が続く場合、うつが考えられます。
- 気持ちが沈む
- 食欲がない
- 不眠や中途覚醒が頻繁にある
- 希死念慮
- 集中力の低下
不安症
不安症とは、社交不安障害、パニック障害など、強い不安や恐怖心により日常生活に支障が出る状態を指します。
以下の症状などで日常生活に悩んでいる場合、精神科や心療内科を受診すると原因の特定・対処ができるかもしれません。
- 突然動機やめまいがする、発汗・手の震えなどがある(パニック障害)
- 人前で頭が真っ白になる、手足や声が震える(社交不安障害)
- 小さなことで不安になる、自然災害や紛争が不安で眠れない(全般不安症)
HSPは生きづらいのか
「HSPは生きづらい」と言われることがありますが、本当にそうなのでしょうか。
実際は、HSPだから必ずしも生きづらいというのではなく、単に環境からの影響を受けやすいだけなのです。
悪い環境から悪い影響を受けることは確かに「生きづらさ」に繋がるでしょう。
しかし、良い環境からは良い影響を受けやすいというメリットを忘れてはいけません。
これまでご説明してきたDOESの中でも、それぞれ良い面もあれば悪い面もありますよね。
自分にとって悪い環境を避け、良い環境を整えることで、人よりも生きやすくなり得ます。
「自分はHSPだから生きづらいのだ」と思ってネガティブなことにばかり目を向けてしまうのではなく、ポジティブな側面も、見ていくことが大切です。
生きやすくするための方法
生きづらさを感じることがあれば、それを書き出し、改善策を考えてみることが有効です。
例えば以下のようなものが考えられます。
- 人混みが苦手→休日は繁華街には出かけない
- 飲み会から帰るとぐったり→飲み会を断ってみる
- 電車の臭いが気になる→マスクをする
- 長時間誰かと一緒にいるのは疲れる→1人時間を確保する
また、自分にとってよい環境を考え、よい環境に長くい続けられる工夫をすることも大切です。
- 家族と仲良く過ごす
- 落ち着いた部屋で過ごす
- 心地よい香りを身にまとう
- 肌触りのよい服を着る
自分自身の特性を理解し、よい環境に身を置く工夫をすることが、HSPさんが生きやすくなるために重要です。
このブログが少しでもあなたの生きやすさのヒントになれるよう、日々精進してまいります。




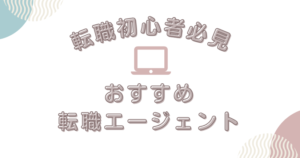
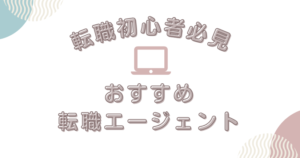




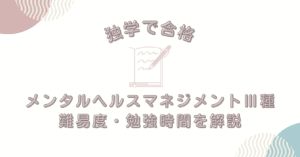





コメント