こんにちは🌼
「ゆるく生きるために こつこつ頑張る」ゆるこです☺️

会社を退職する際、必要な手続きはご存じでしょうか?
私は転職が初めてであり、何をどうすればいいのか全く分からず、困った経験があります。
そこで今回は、退職時の手続きについて、簡単にまとめてみました。
みなさんのご参考になれば幸いです。
1日も空きがなく転職先へ入社する場合、自分で行う公的手続きはありません。
1日でも空きがある場合、健康保険・国民年金・失業保険の手続きが必要です。
前職で持株会・団体保険・企業型確定拠出年金に加入していた場合は、こちらの手続きも忘れずに行いましょう。
健康保険
公的な社会保険制度には加入義務があります。遅延なく手続きを行いましょう。
退職日翌日に転職先へ入社する場合は手続きは不要です。
前の会社へ健康保険証を返却し、転職先の会社から新しい健康保険証をいただきます(入社後3週間前後で届きます)。
退職後会社へ属さない期間が1日でもある場合、手続きは3通りあります。
- 国民健康保険に加入
- 家族の扶養に入る
- 任意継続被保険者制度を利用
詳しく見ていきましょう
国民健康保険に加入
会社の健康保険など、他の保険制度に属さない人が加入義務のある公的な社会保険制度です。
期限:退職後14日以内
場所:役所の国民健康保険担当窓口
書類:
- 健康保険の資格喪失日がわかる証明書(健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 各市区町村で定められた届出書
- 印鑑
保険料:市区町村により異なります
給付内容:健康保険とほぼ同じですが、一般に出産手当金や傷病手当金はありません。
家族の扶養に入る
家族の加入している社会保険の扶養に入ることをいいます。
自分自身で保険料を負担することなく給付を受けられます。
被保険者の要件
- 被保険者の3親等以内の家族
- 同一生計であること
- 同一世帯(条件あり)
2・3を詳しく見ていきます。
2.同一生計の条件
- 被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者は180万円)
- 同居の場合:年間収入が被保険者の収入の1/2未満
- 別居の場合:年間収入が被保険者からの仕送り額未満
年間収入とは、年間の見込み収入額のことです。
雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
3.同一世帯の条件
- 被保険者と同居の必要がない場合
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居が必要
- 上記以外の3親等以内の親族
- 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含みます)
手続き:被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
実際は会社の人事担当が手続きをすることが多いので、扶養に入る旨を報告し確認しましょう。
必要書類例(詳細は会社の人事担当や、近くの年金事務所へ)
- 続柄確認のための書類
- 被扶養者の戸籍謄本
- 住民票の写し
- 収入要件確認のための書類
- 退職証明書
- 年金額の改定通知書
- 直近の確定申告書
- 別居の場合、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
- 内縁関係を確認するための書類
- 両人の戸籍謄本
- 被保険者の全員の住民票
任意継続被保険者制度を利用
これまでの健康保険を任意継続することを言います。
退職前の被保険者期間が2か月以上あれば、退職後2か月間、在籍中と同じ健康保険に加入することができる制度です。
手続き期限:退職後20日以内
場所:加入していた健康保険組合または居住地域の社会保険事務所
必要なもの:
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- 住民票
- 1か月分(退職日により2か月分)の保険料
- 印鑑
保険料:被保険者が全額自己負担(それまでの負担額の倍程度)
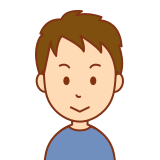
任意継続と国民健康保険、どちらが得?
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なるため、一概には言えません。
役所のHPでも計算方法が掲載されていることがあるので、調べてみましょう。
年金
再就職する場合は、再就職先の厚生年金保険へ加入することになります。
基礎年金番号の分かるものをコピーし、会社の人事等へ確認しましょう。
保険料は被保険者と事業主が折半で負担し、給料から控除されます。
退職後会社へ属さない期間がある場合、手続きは以下の2通りです。
- 国民年金に切り替える
- 配偶者の扶養に入る
国民年金に切り替える
期限:退職後14日以内
場所:役所の年金窓口
保険料:年度によって変動します。令和4年度は月額16,590円
以下のような場合には免除制度があります。該当する方は日本年金機構のHP等で詳しく確認しておきましょう。
- 法定免除
- 障害年金の受給者
- 生活扶助受給者など
- 申請免除
- 前年の所得が一定基準以下
- 被保険者や家族が生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 地方税法の障碍者・寡婦またはひとり親に該当し所得が非課税限度額以下
- 天災や失業で保険料を納めることが困難な事情にあるとき
配偶者の扶養に入る
期限:退職後14日以内に被保険者の会社へ申請
保険料:被保険者が加入している厚生年金保険や共済組合から拠出されるため、個別での負担はありません。
被保険者によって生計が維持されていることが条件となり、以下の認定基準があります。
- 日本国内に住所を有すること
- 年収が130万円未満であること
- 別居の場合、年収が130万円未満かつ被保険者からの援助額より少ないこと
失業保険
雇用保険の基本手当のことです。失業手当とも言われます。
受給期間は離職日の翌日から原則1年間です。この中で待期期間や給付制限期間等を経て、基本手当を受給しなければなりません。申請が遅くなると、受給期間が短くなってしまいますので、退職後の申請は速やかに行いましょう。
手続き:
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで離職票と求職票の提出
- 7日間待機
- 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
- 1週間程度で失業保険の初給付

持株会
持株会を利用していた方は、個人口座へ振替する必要があります。
- 個人口座の開設
- 持株会が委託している証券会社の個人口座の開設が必要です。
- 持株の振替手続き
- 2週間~1か月程度の時間がかかります。
口座開設~振替完了まで時間がかかるため、退職を決めたらすぐに口座の開設を行いましょう。
団体保険
勤務先の団体保険によって取り扱いが異なるため、確認が必要です。
主に4通りに分かれます。
- 現在の条件のまま継続
- 給与天引きができなくなるので、保険料の支払方法が変更となります。
- 条件付きで継続
- 補償内容が減額になるなど、一部変更され継続することができます。
- 継続不可
- 退職者は加入できず、自動的に解約となる場合です。
- 退職者向けの商品
保険の内容を見直すいい機会になりますね。
確定拠出年金
勤務先の企業型確定拠出年金に加入していた場合は、移換手続きが必要です。
退職後6か月以内に手続きを行わなければ、国民年金基金連合会へ自動移換されてしまいます。管理手数料が差し引かれる・運用の指図ができない・資金に利息が付かない等のデメリットがありますので、忘れずに手続きを行いましょう。
- 勤務先に企業型確定拠出年金がある場合は、そちらへ移換
- 勤務先から資料を取り寄せ、手続きを行います。
- 企業型DCがない場合、個人型(iDeCo)へ移換
- iDeCoを始めたい証券会社・銀行から資料を取り寄せ、手続きを行います。
損をしないためにも、以上の手続きを忘れずに行いましょう!

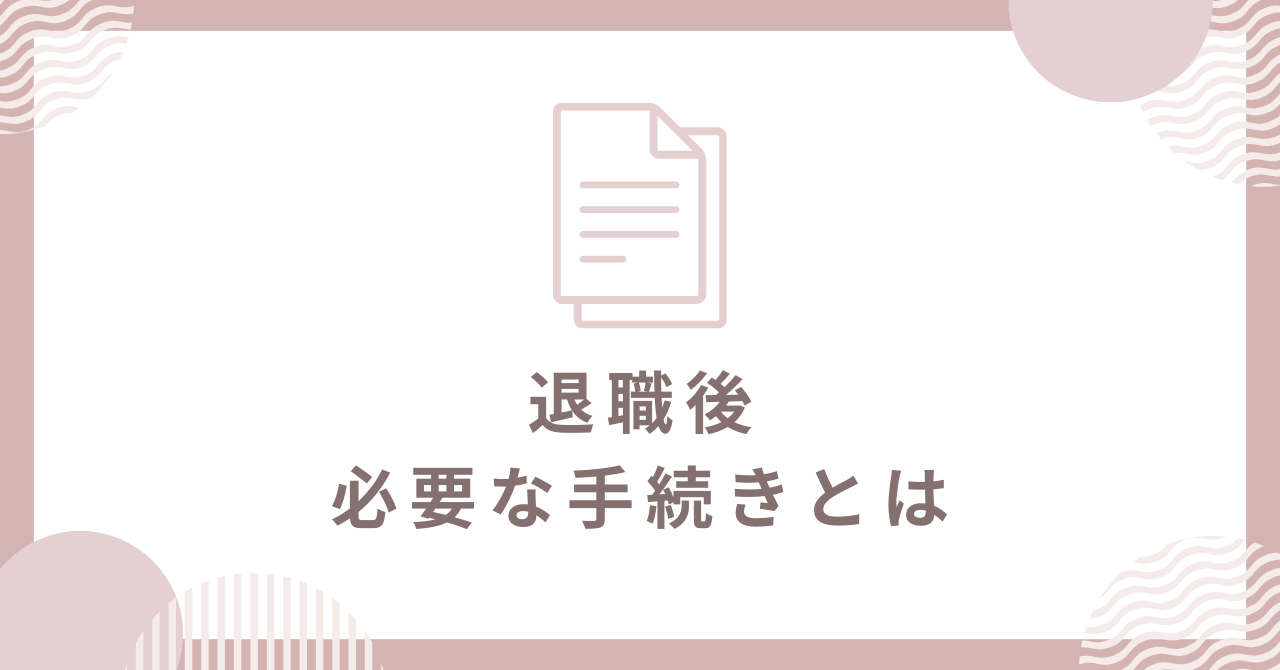


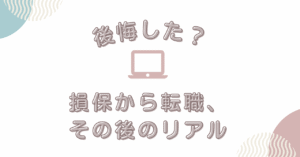
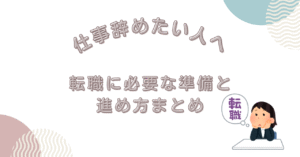



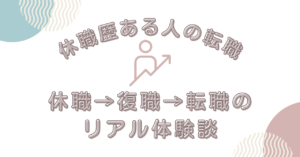

コメント